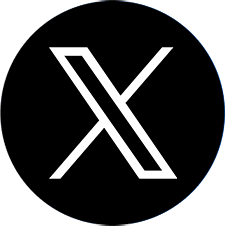「LINEヤフーのバリューとは何か」CPO 慎ジュンホ×人事担当役員・坂上対談
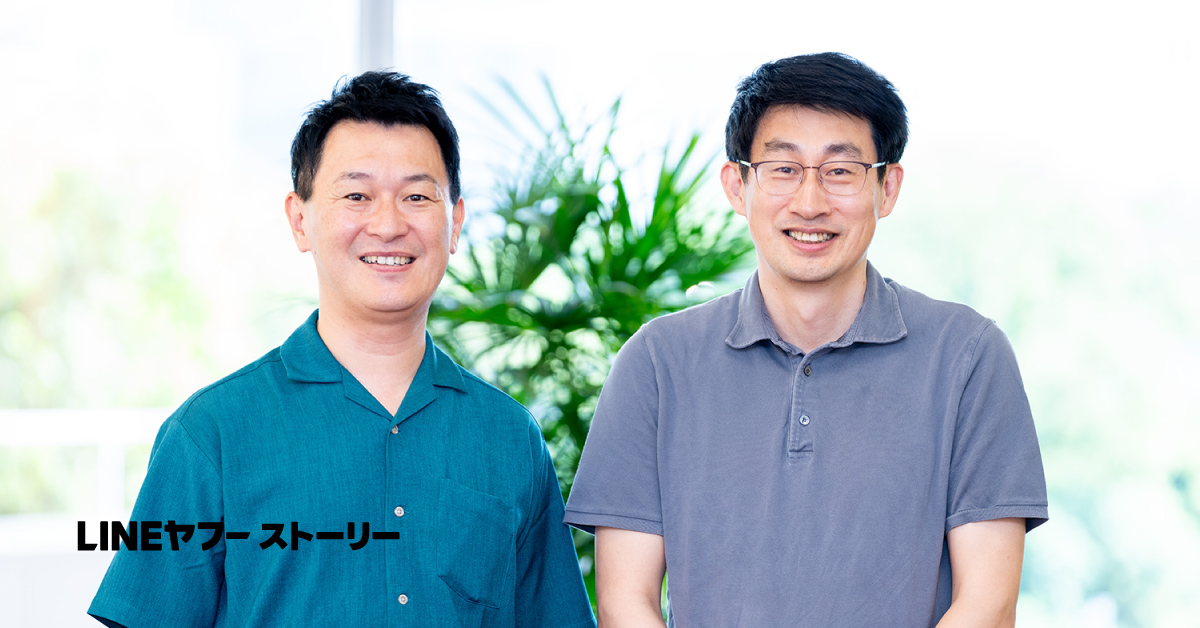
LINEヤフーグループには、「ユーザーファースト(Users Rule)」「やりぬく(Get It Done)」「少数精鋭(Lean & Mean Teams)」を中心としたバリューがあります。
今回は、バリュー策定の中心人物であるCPO(Chief Product Officer)の慎 ジュンホと、人事担当役員の坂上 亮介に、「LINEヤフーのバリューとは何か」という問いを投げかけ、策定意図や背景、各項目に込められた思いをたっぷりと語ってもらいました。
LINEヤフーグループの「DNA」
――そもそも、会社のバリューって何のためにあるのでしょうか。お二人の考えを聞かせてください。
慎:
会社って、人が「自分ひとりではできないこと」を実現していく場所ですよね。無限の可能性がある中で、人それぞれに人格があるように、会社にも人格のようなものがあると思うんです。それを表現しているのがカルチャーです。
また、人に「DNA」があるように、会社特有の「DNA」に相当するのがバリューだと思っています。いろんな考えの人たちが集まる中で、大切にしている価値観や方向性を明文化しないと、会社が目指すものを共有できませんよね。人が「DNA」を持つように、会社も「DNA」をしっかり明文化しないと同じ方向に進めない。これはわれわれだけでなく、一般的にもバリューが重要だと考えられている理由だと思います。

坂上:
LINEとヤフーが合併しているのもそうだし、この会社が1社目の人もいれば、他社から転職してきた人もいますよね。いろんなカルチャーを経験してきた人たちがいる中で、LINEヤフーとしての価値観や仕事をする上での基準をきちんと明文化したのがバリューだと思います。
「ユーザーファースト(Users Rule)」が9割
――いまのバリューをつくる上で重視したポイントは?
慎:
バリューBOOK(※)ではページの構成上、3つのパートが並列に置かれていますが、一番重要なのは「ユーザーファースト(Users Rule)」です。「やりぬく(Get It Done)」「少数精鋭(Lean & Mean Teams)」は手段の話なので。ユーザーを理解したうえで、ユーザーが求めるもの、使い続けるものを提供しなければならない、と考えると、最初の起点も最後の評価軸も、全てユーザーが決めるものです。なので、9割以上の割合で「ユーザーファースト(Users Rule)」が重要だと考えています。

※ LY Corporation Group Our Mission & Values ver.1.0 より
――坂上さんは最初にこのバリューを見たときに、どう感じましたか。
坂上:
LINEもヤフーも似ている要素があったので、あまり驚きはなかったですね。1つ大事だと思ったのが、「大企業病」に陥らないようにしなければならない、という点です。「ユーザーファースト(Users Rule)」にあるように「上司ファースト」じゃダメだし、「少数精鋭(Lean & Mean Teams)」にあるように母艦のような「大規模チーム」じゃダメ。われわれは大きな会社になったけれども、大事にしなければならない部分は、きちんと盛り込まれていると思いました。それから特定の職種に限らず、普遍的な内容になっているので、使いやすそうだなと思いましたね。

バリューBOOKに書かれていないこと
――ここからは各バリューの具体的なイメージについて、お伺いしていきます。まずは「ユーザーファースト(Users Rule)」のパートから。
慎:
「ユーザーファースト(Users Rule)」は、本質的な意味を理解しやすくするために、3つの要素で構成しています。まず1つ目の「データを基に俯瞰で判断(Always Data-driven)」。これには2つ意味合いがあって、実はバリューBOOKに盛り込めていない部分もあります。
データを基に俯瞰で判断(Always Data-driven)
自分だったら使わないプロダクトは、創るべきではありません。一方で、自分しか使わないものも創るべきではありません。そんな壁を打ち破るには、データが必要不可欠です。自分の熱量と市場との差分はどうしても発生してしまうもの。データから、ユーザー本人も気づいていないようなニーズも発掘できます。状況は常に変わりゆくものと捉え、絶えずアップデートする。その積み重ねを怠らず、より良い判断をしていきましょう。
まずは、坂上さんが言っていたように、何かの意思決定をするときに、大事なのは、「それがユーザーにとって良いものなのか」というところです。権威だけで意思決定すると、やっぱり失敗するサービスになります。そこにユーザーがいないので。じゃあ、ユーザーの声を反映させるには、どうすればいいか。データがユーザーの声を代弁するツールになってくれるんです。その意味で「データドリブン」と言っています。
もう一つ、それよりも重要なポイントは、「データが全てではない」ということです。ユーザー自身も自分が何を求めているのか、わからないからです。でも、あとで使ってみたら、「これこそ自分が求めていたものだ」と思ったりする。たとえば、スマホが登場したときに、「いまの携帯電話に不満がありますか」と聞いたら、9割以上は「不満がない」と答えたでしょう。でも、実際にスマホを経験したら、「やっぱり、こっちを求めていたんだ」と気が付くようになる。

慎:
なので、より重要なのは、ただデータドリブンであれば良いのではなく、「データドリブンですらなければ、何もできない」ということです。ベースとしてデータドリブンでありながら、最後はユーザー自身もわからない、「WOW」や「!」を狙わないと成功できません。全てはユーザーのためであって、ユーザーを最優先するための手段としてデータがある。データが全てじゃなくて、基本の「基」なんです。データドリブンじゃないと、「サービスをつくる資格がない」というレベルの話です。
細部へのこだわりが違いを生む(Perfect the Details)
細部へのこだわりや、完成度こそが、ユーザーやクライアントの心を動かします。その積み重ねによって、他ではなく、私たちを選んでいただけるのです。ユーザーやクライアントが見ている景色を解像度高くイメージし、細部に至るまで改善を重ねましょう。
「細部へのこだわりが違いを生む(Perfect the Details)」で伝えたいのは、たとえば、レストランに行ったときにどんなに料理がおいしくても、テーブルが汚いとか、接客する人の態度が悪いとか、細かいところでがっかりしたりするじゃないですか。超一流と言われるレストランは、全てが完璧で、1ミリの誤差もないほどの質を追求していますよね。それと同様に、ユーザーが求める最高のサービスを提供するためには、細部へのこだわりを徹底的に追求しなければならない、ということです。
そして、「完璧なもの」は、「そこに要らないものが1つもないこと」なんですよね。たしか誰かの名言だったと思います(※)。つまり、「細部へのこだわりが違いを生む(Perfect the Details)」の真意は、「細かい部分を増やすこと」ではなくて、要らないものをなくして「シンプルにすること」なんです。これは誤解がないように伝えたいです。完璧なデザインはシンプルです。いろんな機能を全部見せて複雑にすることは、「Perfect the Details」ではありません。ただ質が低いだけです。
※「完璧とは、付け加えるものが何もないことではなく、取り除くものが何もないということである」(アントワーヌ・ド・サン=テグジュペリ)
信頼を勝ち得る(Stay Trustworthy)
私たちが信頼を得るべき相手は、ユーザーはもちろん、一緒に働く同僚、クライアントなど多岐にわたります。信頼を築くことに近道はありません。日々の業務の中で、「何を達成するか」だけでなく、「どのように正しく進めるか」を考えて行動することが重要です。ライフプラットフォームとしてさまざまなステークホルダーからいただいている信頼と期待に、真摯に向き合いましょう。
「信頼を勝ち得る(Stay Trustworthy)」は、より重要性が上がってきている部分です。
われわれは既にYahoo! JAPANやLINE、PayPayなど、社会的なインフラになっているサービスを運営しています。サービスの機能性やデザイン、斬新さも大事ですが、インフラとして信頼できる存在にならないと、結局はユーザーが離れてしまいます。全般的に信頼できるインフラとしての役割を果たそう、ということです。
LINEをつくったときの実体験
――いろんな可能性がある中で、どうやって3つの要素に絞っていったのですか。
慎:
「ユーザーファースト(Users Rule)」を的確に表現するために、経営陣でかなり時間をかけて議論しました。幅広い意見を聞きながらドラフトを重ねて、最終的に3つの要素に絞り込んで。さきほど「データを基に俯瞰で判断(Always Data-driven)」で補足したように、実はほかにも言いたいことはあるのですが、1ページで表現しようとする中で、いまの形に落ち着きました。
――内容には、慎さんご自身の体験も反映されているのでしょうか。
慎:
もちろん。LINEをつくった当時(2011年)、会社として求められていたサービスは、「メッセンジャー」ではありませんでした。誰も「メッセンジャーをつくってくれ」とは言わなかった。でも、当時の日本社会で最もユーザーが求めていたのは「コミュニケーション」だったんです。
LINEというサービスは、「自分たちに何ができるか」よりも、「ユーザーが何を求めているのか」を追求することで、ユーザーの支持を得て成長してきました。自分たちがつくりたいものよりも、ユーザーが求めるものを軌道修正しながらつくっていく方が、100万倍もいい結果になります。それは、僕自身の経験からも言えることですね。

プロダクトづくり以外の視点では
――人事、法務など、バックオフィスの視点では、どんな実践イメージが浮かびますか。
慎:
最近、いろんな方と1on1する機会が増えているのですが、法務の方と1on1すると同じことを言うんです。たとえば、ピアレビュー(※)は、アウトプットの信頼性を高めるためにも重要ですよね。でも、そこはスピードを上げながら、対応する必要があります。ただ形式的にピアレビューを行うだけじゃなく、「ボトルネックがどこにあるのか」「処理時間はどうなっているのか」「最も重要な案件にリソースを配分できているのか」を確認していかなければならない。
※同じ専門職を持つ人がお互いの成果物を評価する活動。
バックオフィスにとっての「ユーザー」は、社内のメンバーですよね。メンバーのニーズやペインポイントを理解したうえで、それを数値化しながら改善していくのが仕事なので、プロダクトづくりと一緒ですよね。それはインフラ部門も、人事部門も、おそらく一緒だと思います。
坂上:
慎さんのいまのお話は、to Bにも共通すると思うんですよね。広告とかセールスプロモーションの立場でも、クライアントのニーズを見ていくのは一番大事だと思いますし、バックオフィスの立場だったら、社内メンバーに対して何を提供しているのかが大事。やっぱり、それをデータで俯瞰的に見ていかないと。
――「信頼を勝ち得る(Stay Trustworthy)」について、坂上さんはどう捉えていますか。
坂上:
インフラとしてユーザー個人の信頼も大事ですし、CFOとしての立場ならば、株主や投資家からの信頼も大事です。「信頼を勝ち得る(Stay Trustworthy)」で重要なのは、「どう正しく進めるか」だと思います。ネガティブなサプライズは一番信頼を失うので、日々のコミュニケーションを積み重ねることですね。その上にようやく信頼ができ上がってくるんだと思います。「何かいっぺんにうまくいく」というものではなくて、真摯に向き合い続けることが大事だと思っています。
指先が考えてくれるまで
――次の「やりぬく(Get It Done)」のパートについてはいかがでしょう? 具体的なイメージを聞かせてください。
慎:
「ユーザーファースト(Users Rule)」を実践するには、「がんばったけど、完成できませんでした」ではなくて、「完成させて、ユーザーを満足させました」と言えるまで、やりぬかなければなりません。努力するだけでは価値がなくて、最後までやりぬくことが重要だと思います。そのためには、時間をうまく使う必要があります。1日はみんな同じ24時間ですので、他社よりも時間を2倍にはできませんよね。同じ時間の中で、やりぬくには、「本質に集中(Work Intensely and Be Focused)」しかないんです。
本質に集中(Work Intensely and Be Focused)
私たちの仕事の本質には、さまざまな要素があります。プロダクトを使ってくれているユーザーのパーセプションは何なのか。提供する裏側にある、ビジネスモデルや市場構造は何なのか。自分が関わる「仕事」を深く理解し、優先順位をつけ、本質的な課題に時間と労力を集中しましょう。同じ時間を使うとしても、ただ一生懸命ではなく、極度に集中しなければ成功にはたどり着けません。LINEヤフーグループで働くひとりひとりにおける大事なスキルです。
つまり、「ユーザーが求める本質は何なのか」「それを実現するために、この機能は本当に重要なのか」と問いかけて、徹底的に本質に集中していく。たとえば、英語を10時間勉強して、うまくなる人とそうじゃない人がいますよね。多少は間違えても「英語で話し続けてみる」とか「徹底的に集中する」みたいな人は、すぐに上達します。でも、「単語をただ暗記しているだけ」では話せるようになりません。
ちょっと話が逸れますが、僕が開発者時代に夢中になって仕事をしていたら、指が勝手に考えてくれることがあったんですよ。

――え、指が考える......?
慎:
そう。脳で考えるのではなくて、指先が無意識に動くような感覚。たぶんものすごく集中すると、どの分野のプロでも、そういう経験をすることがあるはずです。それで、同じ時間でも成果の質が100倍以上変わることもあるでしょう。時間の密度を高くして、本質に集中できるか。それが、「やりぬく(Get It Done)」につながる第一歩だと思います。
――「圧倒的当事者意識と成果へのこだわり(Take the Initiative)」については、いかがですか。
圧倒的当事者意識と成果へのこだわり(Take the Initiative)
自らが関わる仕事には、担当領域だけに留まらず、最後のゴールに至るプロセスすべてにコミットしましょう。それが「圧倒的当事者意識」の意味するところです。代案なき否定や協力なき批判ではなく、前向きに、隣の仲間を助け、最後まで責任を持って取り組むのです。そして成果に対し、みんなで徹底してこだわりましょう。期限と目標を明確に設定し、それに向かって、達成する意識を常に持ち続けることが肝要です。
慎:
大企業になればなるほど、「ポテンヒット」(※)になりやすいじゃないですか。「自分の担当範囲だけを見ていればいいや」って。でも、組織が完璧にかみ合って動いている会社は存在しないので、「ポテンヒット」にならないように、どのポジションの人でもいいから、ちゃんと守備をしなければならないときがあります。ユーザーから見て抜け漏れがあるのに、「ここはわれわれの縄張りなので触るな」とか「自分の仕事じゃないから口を出さない」と言っていては、絶対にいいサービスはつくれません。
※誰が担当するのかがあいまいで、結果的に誰も対応しないまま放置されてしまう業務や問題のこと。もとは野球用語。
「圧倒的当事者意識と成果へのこだわり(Take the Initiative)」をもって、デザイナーじゃなくてもユーザー目線でおかしなデザインがあれば議論したり、エンジニアじゃなくてもサーバーがおかしいと感じたら指摘したり、お互いが自由に意見を言い合える環境にしていく必要があります。
その意味で、僕は「もめられる組織」が大事だと思っています。「もめる」というのは、ただのケンカではありません。お互いに十分な信頼残高があって、だからこそ、遠慮なく意見をぶつけ合える状態のことです。
全員が「ユーザーファースト(Users Rule)」を思い、相手をプロとして尊重していれば、厳しい指摘をしても「ユーザーのために受け入れてくれるはずだ」と信じられます。逆に指摘を受けても、「よくわからないのに口を出すな」とは思わず、「何か問題があるのかも」と素直に向き合えるのです。こういう土台があるからこそ、建設的な議論が生まれます。当事者意識を育む上でも、「もめられる組織」とその背景にある仲間との信頼関係が欠かせないと思っています。
プロフェッショナリズムの徹底(Embody Professionalism)
プロフェッショナルだと誰もが認める人は、どのような人物でしょうか。自身の担当領域において、他の人よりも優れた成果を生み出せる人のことです。ユーザー、クライアント、同僚からの期待を大幅に超えましょう。そうした個が集まることで、組織は強くなり、仕事の質は磨き抜かれるのです。
次の「プロフェッショナリズムの徹底(Embody Professionalism)」もその延長線にあります。お互いを尊重しあえるほどのプロ同士じゃなければ、信頼関係は築けません。
最高のチームワークを実現するには、まずは個人がプロフェッショナリズムを追求すべきだと思います。会社としても、そのための教育支援を用意しなければなりません。たとえ、すぐには結果が出なかったとしても、個人がプロとして成長できる組織を目指すことは、とても重要だと考えています。
もめながら楽しめるか
――最後は「少数精鋭(Lean & Mean Teams)」のパートです。このあたりは、少し誤解を受けやすい部分もあるように思いますが、いかがでしょうか。
慎:
これはチーム体制や意思決定のプロセスの話なんですね。まず、「率直な議論から導く決断(Open Communication & Vertical Decision-making)」は、見えないユーザーニーズを捉えるために、「まずはオープンに議論しよう」ということです。
率直な議論から導く決断(Open Communication, Vertical Decision-making)
地位、役職、年齢を問わず、十分で率直な議論を心がけましょう。そのためには議論に参加するすべての人がターゲットやビジネスモデルに対し、深い理解を持つ必要があります。そうでなければ、率直で意味のある議論はできません。フラットな議論を尽くした後の決断はリーダーの役割です。リーダーは意思決定に責任を負い、メンバーはその決定が自分の意見と違っても、リーダーの判断を信じて一緒に力を合わせ、業務に取り組みましょう。
たとえば、20代女性向けのサービスのニーズを読み取るのは、僕よりも新入社員の方が得意かもしれません。「業界経験30年だし、いつも自分の意見が正しいよ」と思っていると、必ず失敗します。60代向けのサービスであれば、60代のメンバーが一番理解できたりしますよね。その意味で、みんなで知恵を絞らなければなりません。誰が偉いとかではなく、「オープンでフラットな立場でコミュニケーションしよう」というのが、前段の「Open Communication」の意図です。
全ての会議で、誰もが手を挙げて意見を言い合えるのは、正しいあり方だと思います。でも、完璧な意思決定なんてものが存在しない中で、ただ議論だけをしていてもきりがありません。ですので、最初の可能性を広げて知恵を絞る段階ではオープンに議論しながらも、最後は責任者を明確にして、トップダウン(Vertical)で意思決定を行うべきだと考えています。
ゴールに向かって同期し続ける(Keep in Sync with Goals)
世の中の技術は日進月歩です。ユーザーニーズや市場環境、法規制、さらには社員の働き方など、世の中の技術や価値観は刻一刻と変化します。そのため、リーダーとメンバーは目標と方向性を常に明確に共有し、互いにフィードバックを交わす必要があります。チームみんなで認識をアップデートしつづけましょう。
「ゴールに向かって同期し続ける(Keep in Sync with Goals)」も延長線上にあります。ユーザーは「ムービングターゲット」です。ユーザー自身も、自分が何を求めているのかわからない。いまの自分は1年前の自分から変わっていたりするので、「ユーザーファースト(Users Rule)」のゴールは常に動いているのが前提です。なので、いつでも軌道修正できるようにしなければなりません。
チームメンバーにしてみたら、コロコロと方向性が変わると困惑しますよね。でも、「変わるのが当たり前」という認識でいてほしいです。その上でリーダーは、軌道修正する理由をメンバーに説明(Sync)し続ける必要があります。自分の意思決定をひっくり返すのは、「権威が落ちるのでしたくないな」と思うかもしれません。でも、毎日でもいいので、軌道修正すべきところはしてほしい。その代わり、チームメンバーには「なぜそれを変えるのか」を説明し続けてほしいです。
挑戦を共に楽しむ(Enjoy the Challenges Together)
ビジネスとは、本当に困難なものです。市場環境の変化と複雑化はとどまるところを知りません。ただ、一人では越えられない壁を共に働く仲間とぶつかって越えたときの達成感には、言葉にできない喜びがあります。共に楽しみながら意見を交わし、より良いプロダクトを生み出すのです。難しいことへのチャレンジを、いつだって楽しむカルチャーでいましょう。
最後に「挑戦を共に楽しむ(Enjoy the Challenges Together)」。いま言ってきたことは、結局は「苦しいことをやりましょう」ということです。「他社よりも時間密度を高くやる」とか「軌道修正し続ける」とか......全てが苦しい話です。それでも、なぜやるのか。みんなで、他社にはできないことを成し遂げるためです。「絶対にいい結果を出すんだ」と確信したうえで、そのプロセスを一緒に楽しめないと、あまりにもつらいでしょう。本質に向き合うのは大変。でも、仲間たちと前向きに、もめながら楽しみましょう。やっぱり、根底には「楽しむこと」がなければならないと思います。

――「もめながら楽しむ」って、なかなか難しそうだな......とも思います。
慎:
「もめること」って、自分が見えない部分を最短で理解する方法なんです。仲間と議論する理由は、その場で自分にない観点を教えてもらうためですよね。時間をかけようと思えば10時間かかるものが、「いや違うよ」とはっきり言えば、ピンポイントで違う観点がわかる。その意味で、仕事に感情を入れる必要はなくて、議論の場は、「自分の専門性から納得できないこと」をお互いに照らし合わせるプロセスだと考えています。それって楽しいじゃないですか。サッカーチームでたとえるなら、一流の選手たちがボール回しをすることなので。
「人数を減らしましょう」ではない
――「少数精鋭(Lean & Mean Teams)」と、「Open Communication」で広く意見を募ること、のバランスについては、どう考えていますか。
慎:
人数は多ければ多いほどいいと思います。でも貢献しない人がいたら、それはマイナスです。会議のときの僕の基本ルールは、「発言しない人は参加する意味がない」です。知識を照らし合うなら、2人でやるほうが早いじゃないですか。でもそれが3人になる理由は、3人目がプラスアルファの価値を加えてくれるからです。その一方で、コミュニケーションコストは、1人加えるごとに3倍に増えます。その分の価値があるならば、人数を増やせばいい。
これまでのITの歴史で、偉業を成し遂げたチームは例外なく「少数精鋭」です。理由はとてもシンプルで、一番いいものをつくるために「Open Communication」で知恵を絞って、限られた時間で成果を出すために、専門家たちが価値を出し合える最大人数を確保したからです。それが増えすぎてしまうと、コミュニケーションコストだけが3倍になります。結果的にあらゆる「イノベーション」が少数精鋭から生まれてきたのは、個人の力というよりも構造の力だと思います。
「少数精鋭(Lean & Mean Teams)」で伝えたいメッセージは、「人数を減らしましょう」ではなく、「最適な人数を決めましょう」なんです。「少数」ではなくて「精鋭」の方が大事。精鋭チームをつくれば、思いのほか少数になるんですよ。たとえば、3人でざっくばらんに話していたのに、5人に増えたら、急に空気が変わってしまうこともありますよね......。なので、精鋭だけの最適化されたチームをつくりましょう。
――坂上さんの視点ではいかがでしょうか。
坂上:
慎さんのお話に、あえて一つ付け加えるとするならば、「アカウンタビリティ」の側面です。精鋭ならば、ちゃんと自分で説明できると思うんですよね。「誰かに説明をさせる」というのは、やっちゃいけないことだなと思います。それから、日々の軌道修正を説明して、みんなを引っ張れる能力が大事。阿吽(あうん)の呼吸でわかってもらえると思ったら大間違いなので。やっぱり、丁寧に説明する能力が、特に先頭を走るリーダーには大切だなと思います。

――最後に、これらのバリューを実践する社員への思いを聞かせてください。
慎:
LINEヤフーで働くみなさんにとって一番大事なのは、個人の成長だと思います。他社ではできなかったことを、この会社で成し遂げて、ユーザーを感動させるまでの過程は、自分をいろんな面で成長させてくれるはずです。時間は最も貴重な資源ですよね。その時間をみんなでユーザーを感動させるものづくりに使って、結果として、個人も会社も成長すること。LINEヤフーのバリューは、そのためにつくったものです。いいサービスをつくって、「この会社に来てよかったな」と思えるようになってほしいです。
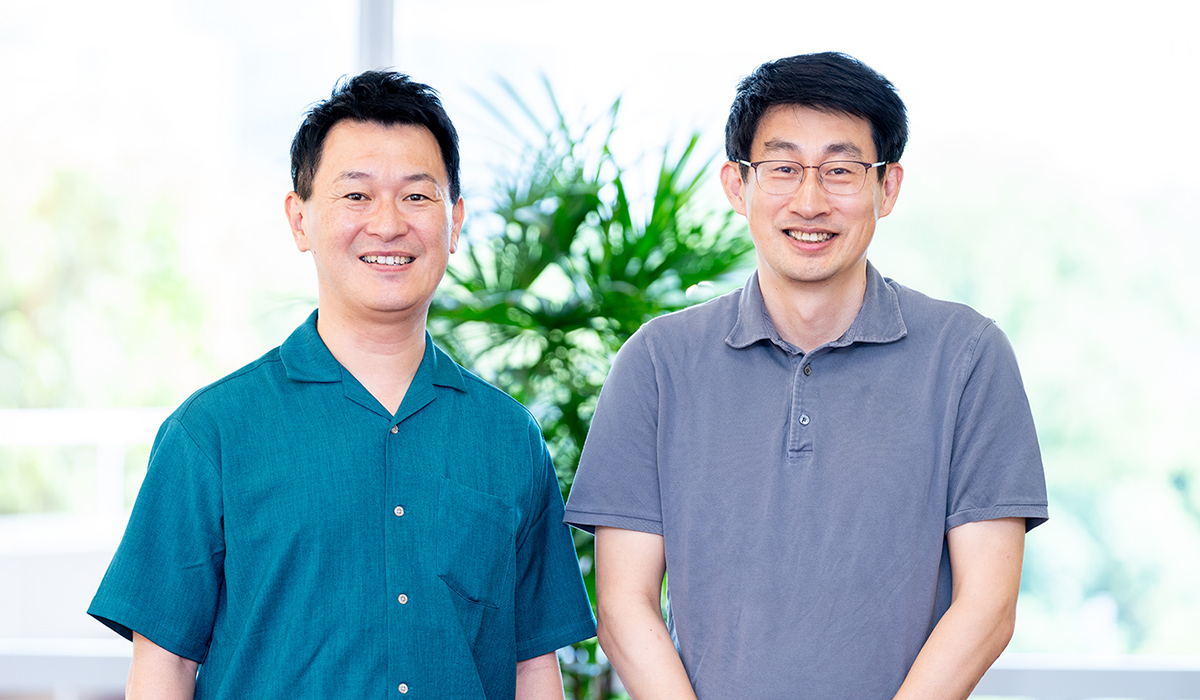
取材日:2025年5月21日
文・LINEヤフーカルチャー推進チーム 撮影・倉増 崇史
※記事中の所属・肩書きなどは取材日時点のものです。

- LINEヤフーストーリーについて
- みなさんの日常を、もっと便利でワクワクするものに。
コーポレートブログ「LINEヤフーストーリー」では、WOWや!を生み出すためのたくさんの挑戦と、その背景にある想いを届けていきます。